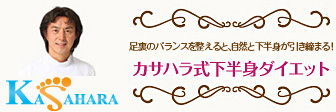
足裏から全身を、"重力とのバランス"で整える!
| 施術予約 | TEL.045-861-8558 | 月~土9:00~19:30 (日曜・祝日 定休) |
|---|---|---|
| 商品案内 | TEL.045-861-8944 | 月~金10:00~17:00 / 土10:00~15:00 (日曜・祝日 定休) |
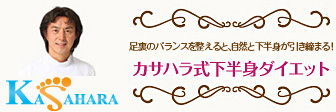
足裏から全身を、"重力とのバランス"で整える!
| 施術予約 | TEL.045-861-8558 | 月~土9:00~19:30 (日曜・祝日 定休) |
|---|---|---|
| 商品案内 | TEL.045-861-8944 | 月~金10:00~17:00 / 土10:00~15:00 (日曜・祝日 定休) |
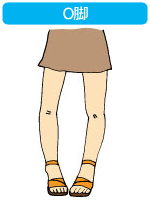 O脚とは、直立したときに、両足・内くるぶしをくっつけても、ヒザや股関節の間が開いてしまう状態のことです。実に、成人女性の約80%が該当しているとも言われているほど、「O脚を気にする人」「O脚にひどく思い悩む人」が急増しております。
なぜ、同じような生活環境にも関わらず、O脚になる人とそうでない人とに分かれるのでしょうか。
その答えが、人間の土台となる『足裏』にあったのです。今、「浮き指」や「外反母趾」「扁平足」など足裏に異常がある人が激増し、これに比例してO脚が増えているのです。
O脚とは、直立したときに、両足・内くるぶしをくっつけても、ヒザや股関節の間が開いてしまう状態のことです。実に、成人女性の約80%が該当しているとも言われているほど、「O脚を気にする人」「O脚にひどく思い悩む人」が急増しております。
なぜ、同じような生活環境にも関わらず、O脚になる人とそうでない人とに分かれるのでしょうか。
その答えが、人間の土台となる『足裏』にあったのです。今、「浮き指」や「外反母趾」「扁平足」など足裏に異常がある人が激増し、これに比例してO脚が増えているのです。
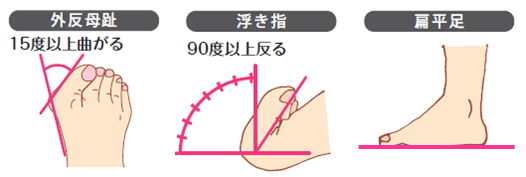 「浮き指」や「外反母趾」「扁平足」があると、指先に力が入らず、重心がかかとへ片寄り、ひざも反り過ぎてしまいます。この状態で歩くと、足先が外方向へ流れる「ねじれ歩行」になるのです。
「浮き指」や「外反母趾」「扁平足」があると、指先に力が入らず、重心がかかとへ片寄り、ひざも反り過ぎてしまいます。この状態で歩くと、足先が外方向へ流れる「ねじれ歩行」になるのです。
 この「ねじれ歩行」になるかどうかで、O脚になる人とならない人に分かれてしまうのです。
つまり、O脚は土台となる足裏の異常を補った結果だったのです。
「ねじれ歩行」によるO脚は、すねの外側の筋肉や太ももの筋肉を発達させて、下半身太りの原因になります。
また、O脚があると健康面でも悪影響を及ぼします。ひざの痛みのほかに股関節や骨盤にゆがみを起こし、背骨が曲がる側弯症の原因にもなっています。更に、首にもゆがみや変形を引き起こし、首こり・肩こり・頭痛・めまい・便秘・冷え性など自律神経失調状態の隠れた原因にもなっています。
家が傾いたら、土台から正していくという考えが自然と起こるように、人間も土台となる『足裏』からO脚を整えていくことが、根本療法につながる近道なのです。
この「ねじれ歩行」になるかどうかで、O脚になる人とならない人に分かれてしまうのです。
つまり、O脚は土台となる足裏の異常を補った結果だったのです。
「ねじれ歩行」によるO脚は、すねの外側の筋肉や太ももの筋肉を発達させて、下半身太りの原因になります。
また、O脚があると健康面でも悪影響を及ぼします。ひざの痛みのほかに股関節や骨盤にゆがみを起こし、背骨が曲がる側弯症の原因にもなっています。更に、首にもゆがみや変形を引き起こし、首こり・肩こり・頭痛・めまい・便秘・冷え性など自律神経失調状態の隠れた原因にもなっています。
家が傾いたら、土台から正していくという考えが自然と起こるように、人間も土台となる『足裏』からO脚を整えていくことが、根本療法につながる近道なのです。


O脚の改善と共に、下半身を引き締める!
O脚には、次の5つのパターンがあります。実際には、O脚は4種類となり、もう一つの足の異常として「X脚」となりますが、ここではあえて「5種類」と表現します。テコの原理で説明すると次のようになります
(1)「ひざ下O脚」のメカニズム
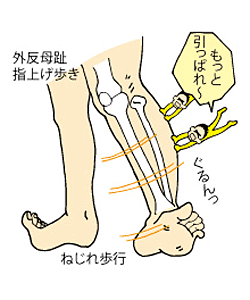 足先が外方向へ必要以上に流れてしまい、「力点」となる。
内くるぶし周辺が「支点」。
ひざ下外側部分にある腓骨小頭部が「作用点」となり、ここへ過剰なねじれのストレスが繰り返されてしまう。結果、腓骨小頭部がゆるんで外側に開き、同時にすねの外側にも余分な筋肉がついてくる。
足先が外方向へ必要以上に流れてしまい、「力点」となる。
内くるぶし周辺が「支点」。
ひざ下外側部分にある腓骨小頭部が「作用点」となり、ここへ過剰なねじれのストレスが繰り返されてしまう。結果、腓骨小頭部がゆるんで外側に開き、同時にすねの外側にも余分な筋肉がついてくる。
(2)「股関節のO脚」のメカニズム
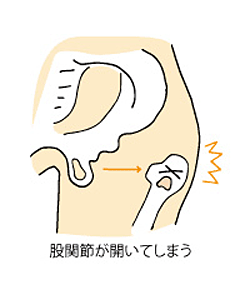 足先が外方向へ必要以上に流れてしまい、「力点」となる。
内くるぶし周辺が「支点」。股関節の外側にあたる「大転子」が「作用点」となり、力が逃げて開いてしまう。
細くても太ももの付け根が出っ張り、股の間が隙間ができるほど開いてしまうのが特徴。
足先が外方向へ必要以上に流れてしまい、「力点」となる。
内くるぶし周辺が「支点」。股関節の外側にあたる「大転子」が「作用点」となり、力が逃げて開いてしまう。
細くても太ももの付け根が出っ張り、股の間が隙間ができるほど開いてしまうのが特徴。
(3)「ひざ下と股関節のO脚」のメカニズム
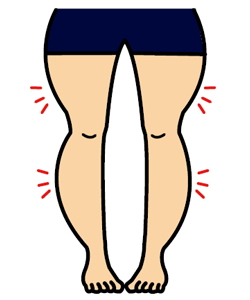 足先が外方向へ必要以上に流れてしまい、「力点」となる。
内くるぶし周辺が「支点」。
ひざ下外側部分にある腓骨小頭部が「作用点」となり、さらにねじれのチカラが股関節にも及び「大転子」も開いてしまう。
つまり、太ももの内側にある大腿内転筋群の締める力が弱いと、脚全体が外方向へ流れて、ひざも開き、太ももやふくらはぎの間も開いてしまう重度のO脚になってしまう。
足先が外方向へ必要以上に流れてしまい、「力点」となる。
内くるぶし周辺が「支点」。
ひざ下外側部分にある腓骨小頭部が「作用点」となり、さらにねじれのチカラが股関節にも及び「大転子」も開いてしまう。
つまり、太ももの内側にある大腿内転筋群の締める力が弱いと、脚全体が外方向へ流れて、ひざも開き、太ももやふくらはぎの間も開いてしまう重度のO脚になってしまう。
(4)「XO脚」のメカニズム
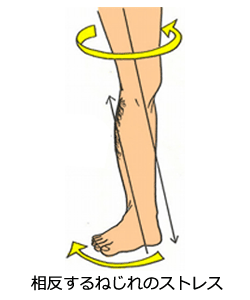 足先が外方向へ必要以上に流れてしまうのが「力点」。
内くるぶし周辺が「支点」。
腓骨小頭部が「作用点」。
ねじれのストレスで外へ逃げる力が働いた場合、その上部は必ず反作用点となる。
このひざを締めようとする力が強いと「反作用点」となり、反作用点の力が勝った場合、大腿骨の下部分が内側にずれてきて両ひざがくっつくが、すね(下腿部)は外側に大きく湾曲した状態になってしまう。更に、股関節の外側に位置する「大転子」も外側に大きくズレて、太ももが外側に太くなってしまう。
足先が外方向へ必要以上に流れてしまうのが「力点」。
内くるぶし周辺が「支点」。
腓骨小頭部が「作用点」。
ねじれのストレスで外へ逃げる力が働いた場合、その上部は必ず反作用点となる。
このひざを締めようとする力が強いと「反作用点」となり、反作用点の力が勝った場合、大腿骨の下部分が内側にずれてきて両ひざがくっつくが、すね(下腿部)は外側に大きく湾曲した状態になってしまう。更に、股関節の外側に位置する「大転子」も外側に大きくズレて、太ももが外側に太くなってしまう。
(5)「X脚」のメカニズム
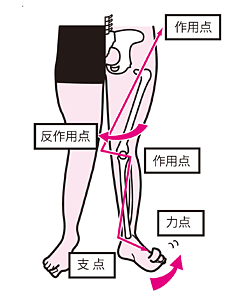 X脚は、足裏が外側を向く「外反扁平足」傾向にあり、足先全体が外側に流れてしまい、「力点」となる。
内くるぶし周辺が「支点」。
ひざの中心付近が「作用点」となり、力が外側に逃げる。
ひざを締める力が強いと、ひざの内側が「反作用点」となり、両ひざはつくが、ひざ下が「ハ」の字になるX脚になる。
更に、大転子が作用点となり、外側にずれて、太ももが太くなる。
X脚は、足裏が外側を向く「外反扁平足」傾向にあり、足先全体が外側に流れてしまい、「力点」となる。
内くるぶし周辺が「支点」。
ひざの中心付近が「作用点」となり、力が外側に逃げる。
ひざを締める力が強いと、ひざの内側が「反作用点」となり、両ひざはつくが、ひざ下が「ハ」の字になるX脚になる。
更に、大転子が作用点となり、外側にずれて、太ももが太くなる。
指先とかかとに薄手のパイル編みで心地よいクッション性。足裏の縦横アーチを作る2本のテーピング機能と、ひざ下の外側をギュッと押さえるO脚補正機能でまっすぐひざに!O脚の原因となる足裏のゆがみと一緒に対策
3本指 & 2本のテーピングサポーター機能で、ゆるんだ足裏のアーチをサポートし、指を踏ん張った正しい歩行を促します。外反内反Wサポーター+外反内反くつ下でさらにサポート力を強化!!
人工筋肉素材「ソルボ」の心地良いクッション性で、地面から繰り返される過剰な衝撃とねじれを吸収無害化し、足・ひざ・腰・首を守ります。
おうちでエステ!軽くて丈夫な素材で新登場!加圧トレーニング作用で首のシワ・たるみ・二重あごがスッキリ!つらい肩こり・首こりにも最適!空気量で微調整できて首らくらく!
カサハラ式骨盤&股関節用「ココベルト」で、骨盤と股関節を強力にサポート!骨盤のゆがみ・腰痛・股関節の痛み・ももが出っ張るO脚などの対策に
股関節と大腿骨をつなぐ「大転子」を引き締めることで、骨盤と体のゆがみを改善し、お尻と太ももの余分な肉をなくしてくれます。
太る理由は足裏にあった! そのメカニズムと対処法が詰め込まれた一冊です。 付録の『つま先サポーター』で足裏のバランスを整えましょう。
O脚は見た目に悪いだけではなく、カラダの不調のモト。不調の原因、O脚がいくつかの方法ですぐに治る!